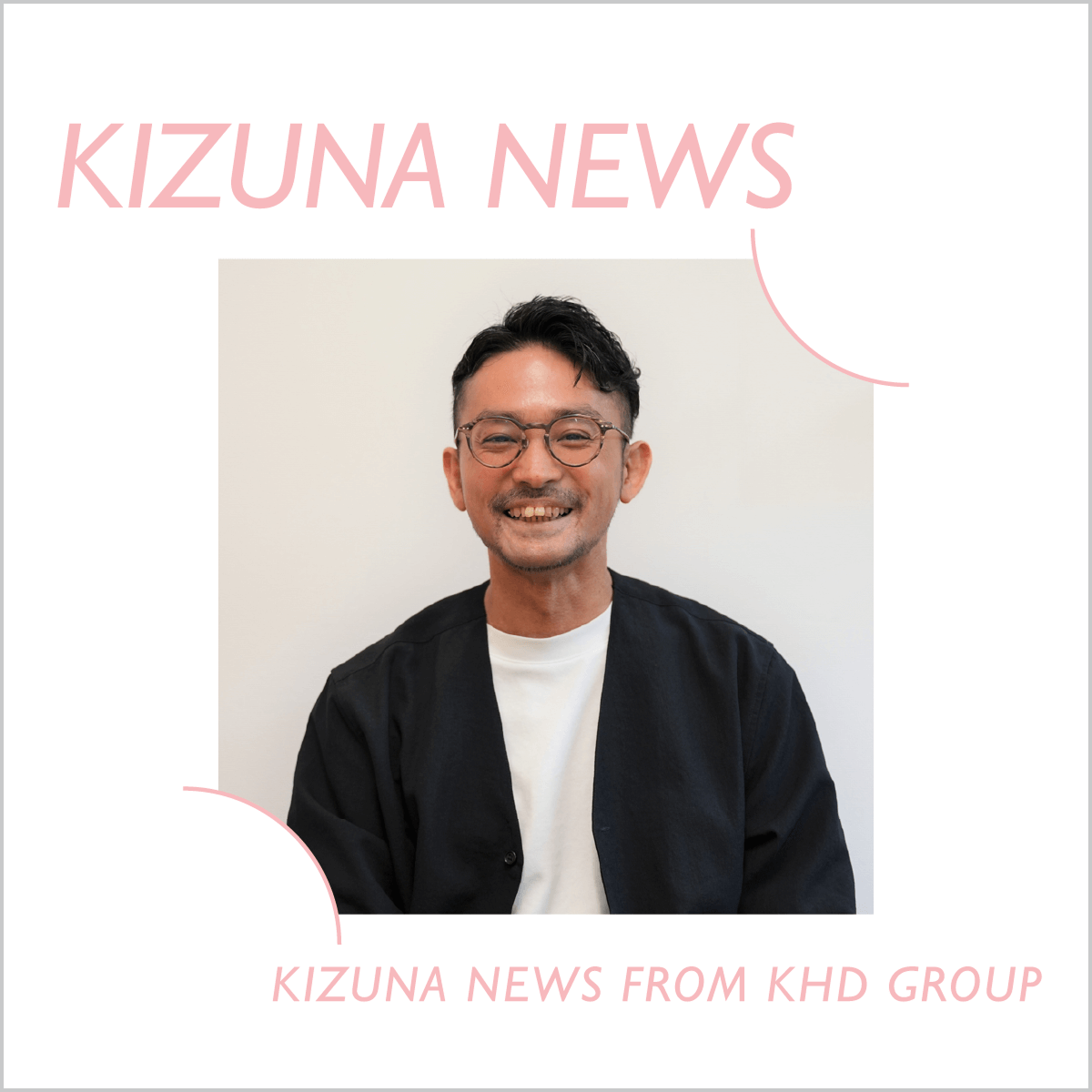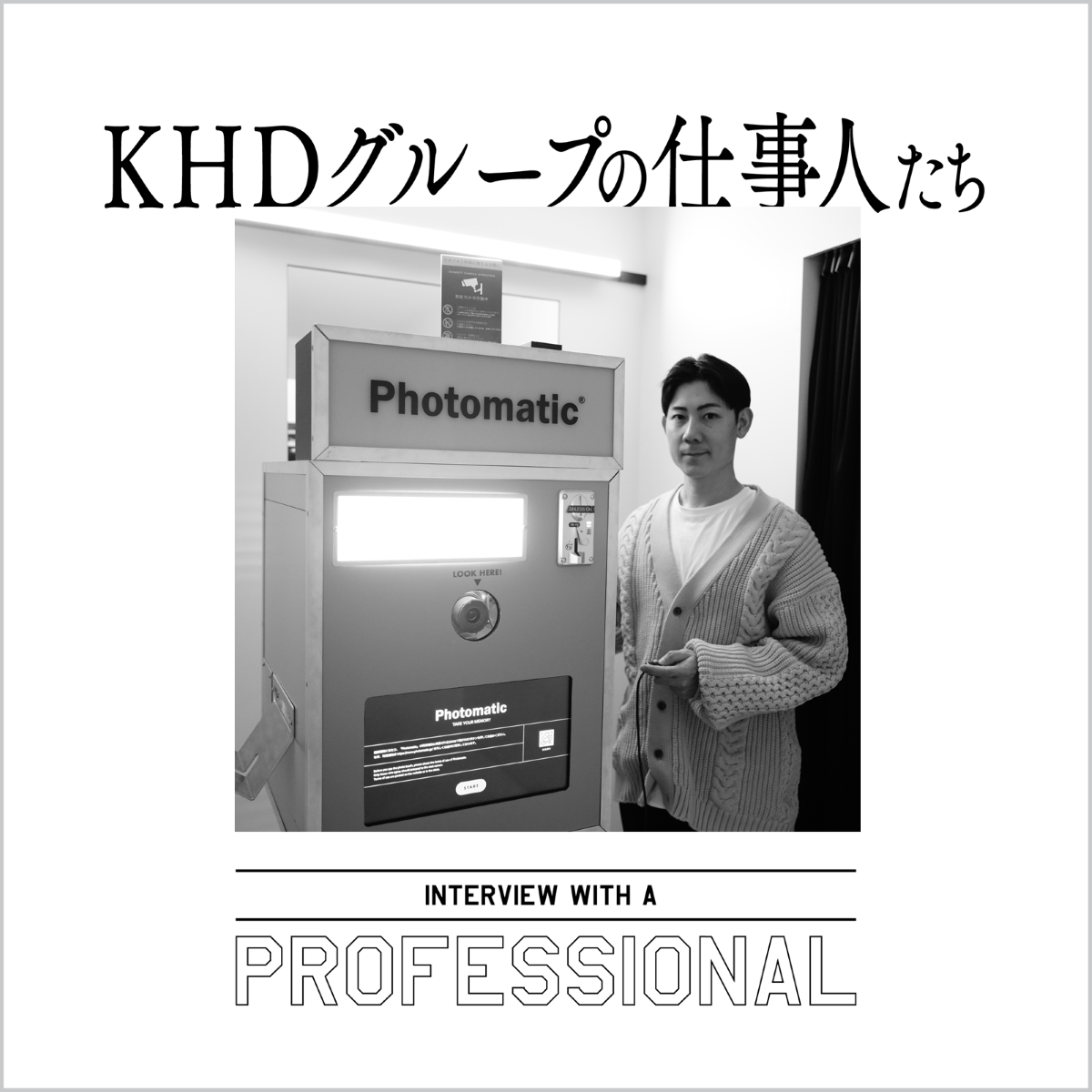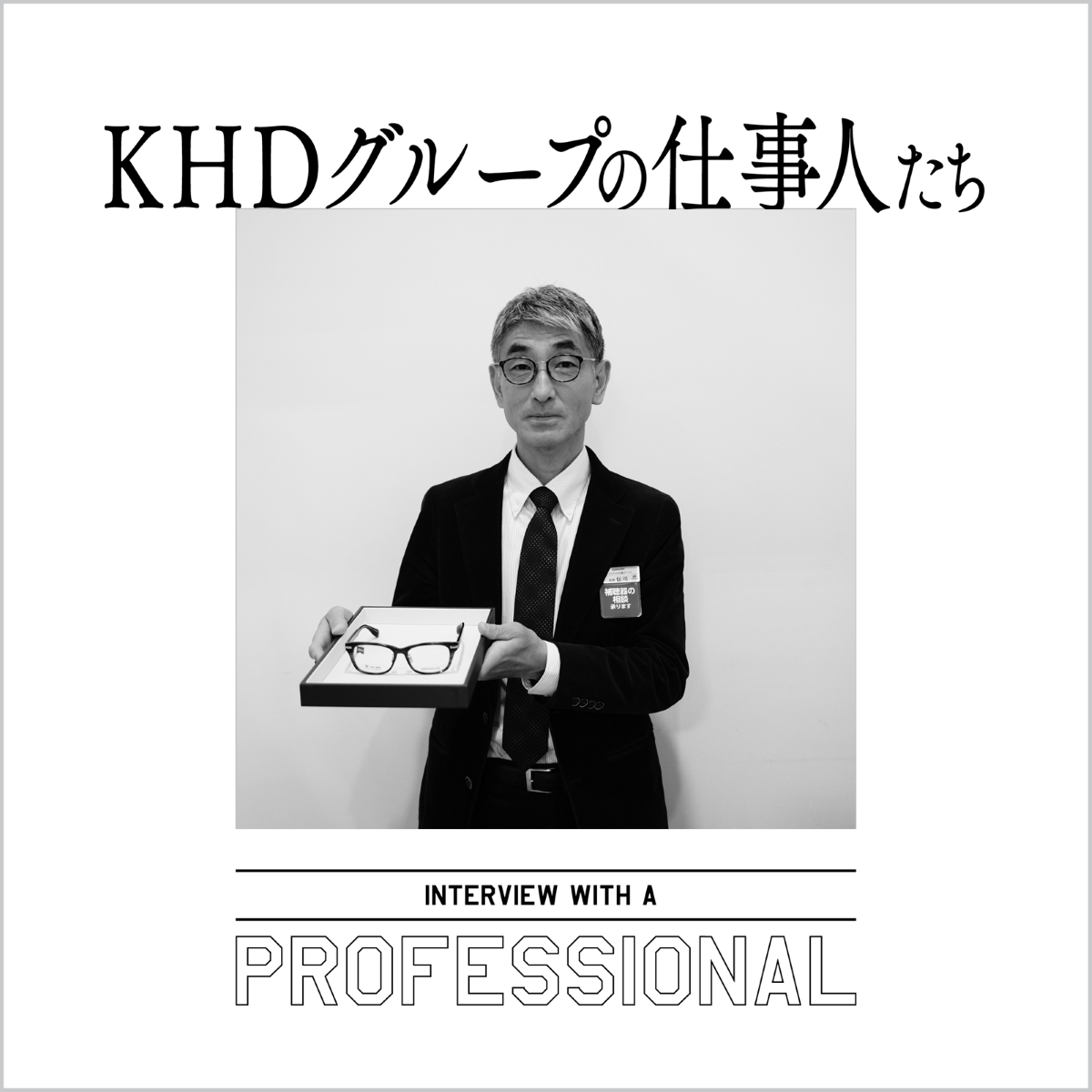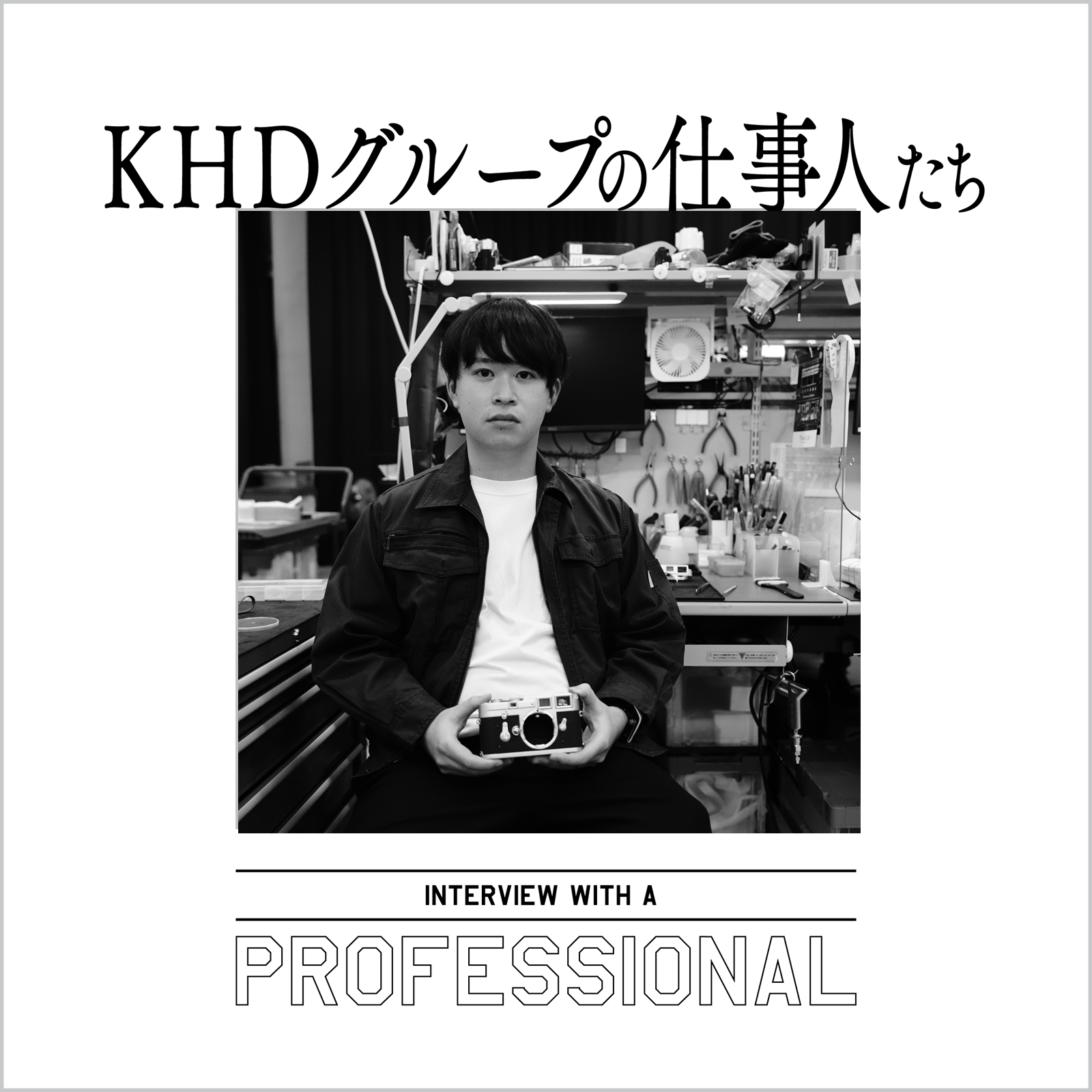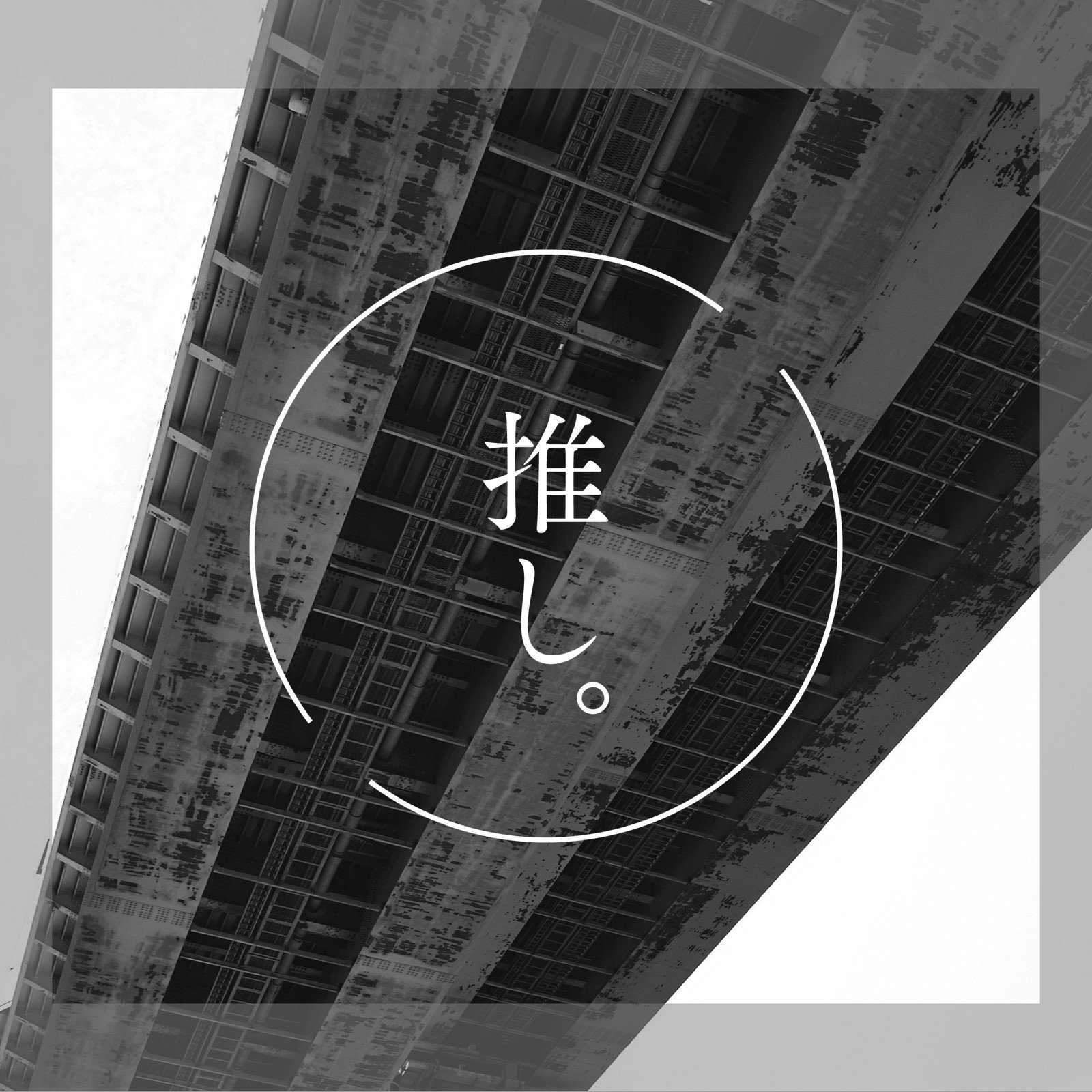本連載の3回目に登場いただくのは、フォトクリエイトの開発部を牽引する 林 裕一郎さん。インターネットで写真販売をしているフォトクリエイトのサービスは膨大な情報量を処理するシステムや、安心安全なセキュリティシステムに支えられています。システム開発を統括する林さんに、ご自身のバックグラウンドから近年話題の生成AIとの働き方についてお話しいただきました。
PROFILE
林 裕一郎 さん
YUICHIRO HAYASHI
新卒でシステム開発を行う会社に入社後、株式会社コトコトの初期メンバーとして設立に参加。2017年に同会社がフォトクリエイトに合流。その後、しまうまプリント・フォトクリエイトの2社を横断するテクノロジー推進部の部長を務め、現在はフォトクリエイトの開発部部長として、システム運営・開発からメンバーのマネジメントを行う。
技術はあくまでも手段としての選択にすぎません。手段で何を成すかが重要なのです
林さんは、キタムラ・ホールディングス グループにおいても、生成AI活用の豊富な知識を持ち、システム開発においても高い技術力を有する一人として有名だ。Cognition社のAIエージェントソフト「Devin」を先駆けて導入し、事務業務などを1名増員したかのようなスムーズさで処理する体制を築き、グループ他社にも横展開するためのワークショップを開くなど、グループ内でのAI活用の第一人者となっている。
またフォトクリエイトのシステム開発分野でも、手動で行っていた写真の判別作業を自動化するシステム「AIセレクト」を構築・実装させ、卓越した技術で高い効率性を実現している。近年、話題となっている「AI×働き方」について林さんはどのように考えているのだろうか。
「AIの導入により、短時間でコードが書けるようになったため、エンジニアはシステムの構築部分など上流部分の仕事ができるようになりました。とはいえ、AIはあくまでも手段としての選択肢でしかありません。手段を使って何を成していくのかが重要だと思います」
高度な知識・技術を手段とするなら、林さんは”今まで”何を成してきたのか、”これから”何を成したいのかを訊いてみた。
つくりたいものを、ずっとつくり続けてきました
林さんにとってのインターネット原体験は小学生時代に遡る。小学校のパソコン室にあったMac(アップル社のデスクトップパソコン)を使って、自己紹介をHTMLで作ったことが初めてインターネットに触れた体験であった。これがとても楽しく、鮮明に記憶に残った 。さらに高校時代には、プログラミングを独学で学ぶ中でインターネットの世界に魅了され、情報系の専門学校に進む。
卒業後にシステム開発を行う会社に入社する。その会社で一緒に働いていた門松 信吾さん(フォトクリエイトでスクール事業や開発システム事業を牽引)に出会い、株式会社コトコトの設立に参画。コトコトは、こどもの成長シネマDVDが作れるアプリ「filme」を運営していた会社で、林さんはそのアプリ開発を担った。
「ご飯を食べる時間すらも惜しみながら、ずっとコードを書き続けていました。つくったアプリケーションをお客さまに初めて使っていただいたことは、たかが数百円の売上でしたが、今でも鮮明に覚えています。お客さまから御礼の手紙などもいただき、規模は小さいながらにToCの体験ができたのが本当に嬉しかったです。つくりたいものをずっとつくり続けていて、本当に研ぎ澄まされた時間でした 」
企業から受諾して指示通りに行うシステム開発ではなく、初めて自分たちが届けたいサービスを開発できたときの喜びを、昨日のことかのように話す。
愚直にお客さまの声を聞きながら形にしていく
仕事に対するお話をお聞きする中で、林さんは、繰り返しチーム作りに対しての言葉を発していた。林さんが率いる開発部に所属するエンジニアはリモートワークがほとんどで、個人作業がかなり多い。そういった働き方の部署をどうマネジメントしているのだろうか。
「大きなプロジェクトや煩雑な課題を解決するには、チームをしっかりとつくることが大事です。そのために、朝会や定例会などでコミュニケーションを活発に行い、リモートワークでも孤独感がないようにすることで、チームの団結力を高めています」
団結力が高いチームを実現するために、 Gather(バーチャルオフィスアプリケーション)やNotion(情報集約クラウドツール)など当時の最新のアプリケーション を積極的に導入して働きやすい環境をつくった。だからこそ、林さんが率いる開発部はリモートワークが多いにも関わらず、他部署に対しても受け手姿勢ではなく、積極的に問題解決のためのコミュニケーションを欠かさない。
それでは、エンジニアの仕事については、どのように思い描いているのだろうか。
「 AI導入により、エンジニアが1つしかできなかったことが2つ、3つできるようになってきました。複数のエンジニアが分業制で行っていた仕事も、一人のエンジニアでできるようになります。事業ごとにエンジニアを配属して、 もっとみなさんの声をキャッチできるようにしたいです」
そして最後に、AIの可能性にふれて、こんな話をしてくれた。
「フォトクリエイトのサービスを使ったお客さまに感動してもらえたり、喜んでもらえるようにするために、やりたいシステム開発・改善はたくさんあります。AI時代が到来したことにより、できることが増えたので、愚直にお客さまの声を聞きながら感動をカタチにしていけたらと思います」
HAYASHI'S WORKS

AIセレクト
写真セレクト作業を大幅に短縮
社内にプロジェクトチームを立ち上げ、林さんはマネジメント及び、開発業務を担当。フォトクリエイトの商品の一つである 「GRAPHICBOOK(団体スポーツ向けに展開している写真集)」で目視判別する写真のセレクト作業をAIで自動化し、フォトグラファーの負担を大幅に削減するとともに、お客さまに商品が届くまでの時間を短縮することが可能になった。
RECOMMEND ISSUE
\あわせて読みたい/
BACK NUMBER
\バックナンバー/
PICK UP
\オススメ記事/